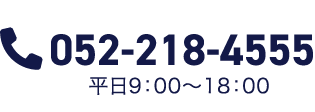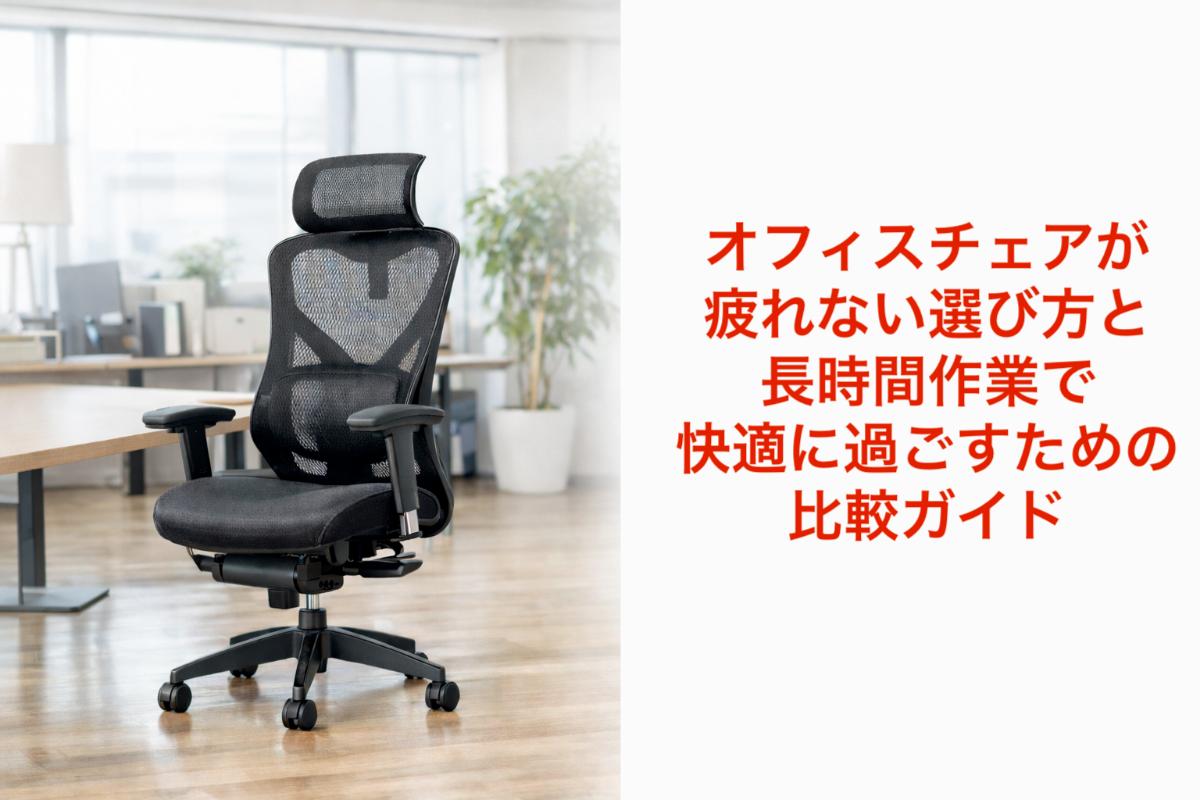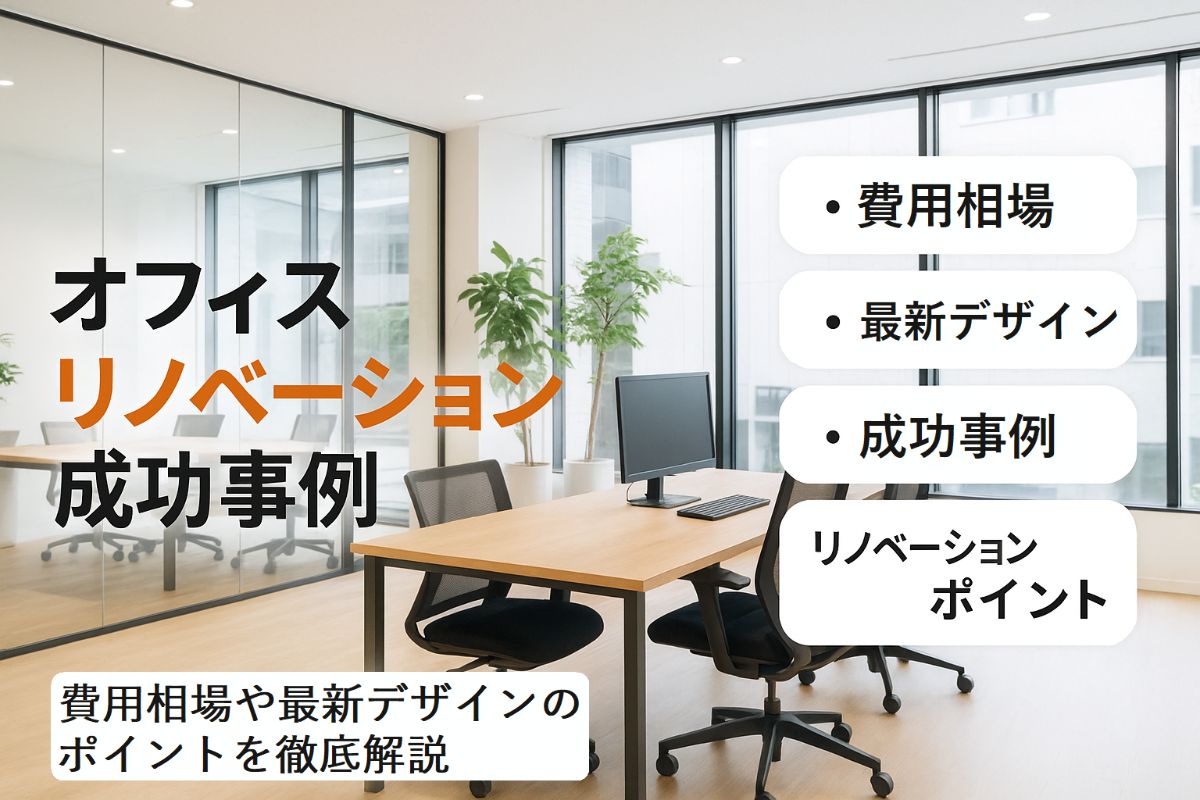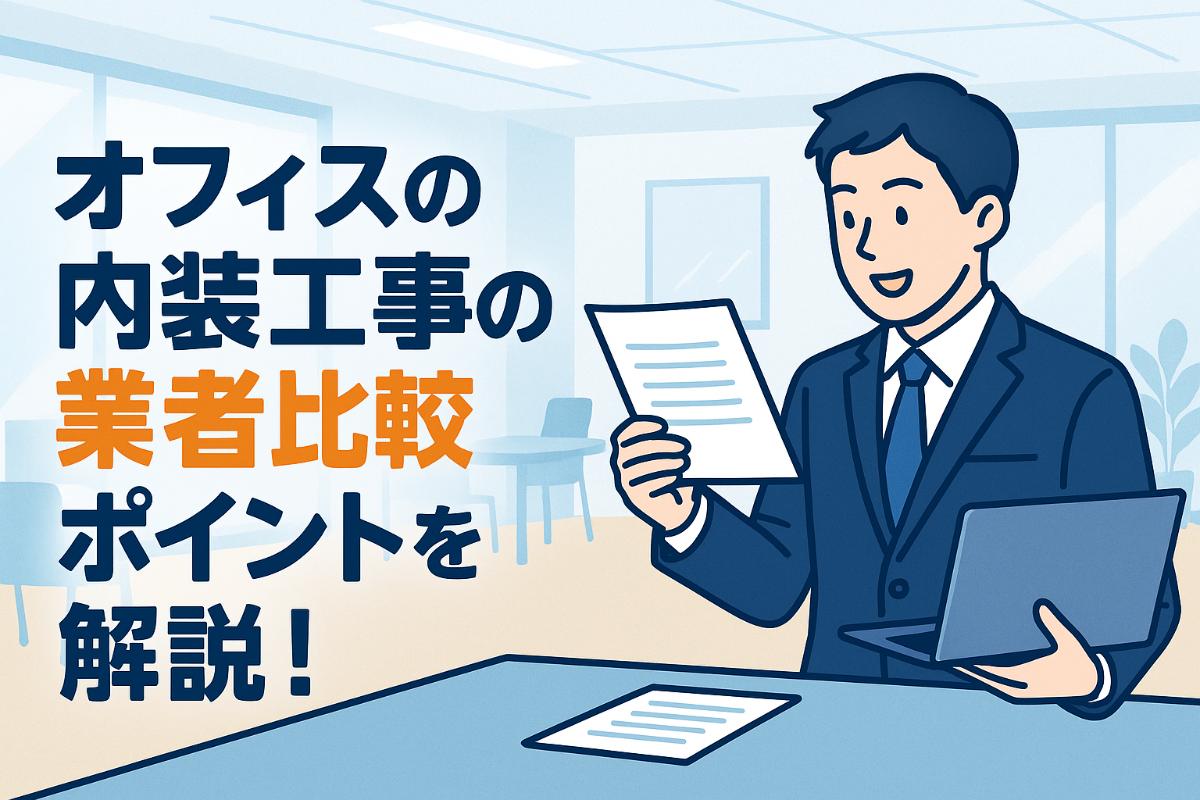不動産コラム
2025年4月18日
オフィスレイアウトで差がつく配置の工夫による快適で効率的な空間づくり

業務効率を上げたい、でもオフィスの空間が限られていてどう配置すればいいかわからない、そんな悩みを抱えていませんか。
実際、多くの中小企業やベンチャー企業では、社員の集中力を維持しながら、コミュニケーションも活性化させるためのレイアウト設計が課題となっています。デスクやチェアの寸法を適切に配置するだけでなく、通路の幅や動線、業務内容に合わせたワークスペースの設計が求められる現代のオフィス。従業員の働き方にフィットしない配置では、ストレスや生産性の低下といったリスクも見逃せません。
オフィスレイアウトは単なる家具の並べ替えではなく、企業全体のパフォーマンスを左右する重要な戦略の一つです。効果的なゾーニング、快適な空間づくり、会議室や執務エリアの配置まで、成功の鍵は空間をどう活用するかにあります。
小規模オフィスや限られたスペースでも、正しい方法を知れば十分に快適で効率的な環境を実現することは可能です。放置すれば従業員のモチベーション低下にもつながるかもしれません。今、空間設計を見直すことで、より快適で生産性の高いオフィス環境が手に入ります。
株式会社ビルプランナーは、お客様のニーズに合わせた不動産仲介サービスを提供しております。テナントの物件探しから不動産の売買、有効活用のコンサルティング、そして賃貸ビルやマンションの建物管理まで、幅広いサービスでサポートいたします。市場動向の精密な分析と豊富なデータに基づき、お客様の不動産活用をトータルでサポートします。どうぞお気軽にご相談ください。
-
-
会社名 株式会社ビルプランナー 住所 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番14号 電話 052-218-4555
オフィスレイアウトの考え方と今の主流
働きやすさと機能性を両立する空間設計
現代のオフィスレイアウトにおいて、働きやすさと機能性を高めることは、企業の生産性や社員の満足度に直結する重要な要素です。従来のように単純にデスクを並べるのではなく、業務内容やコミュニケーションの在り方に応じて、空間を柔軟に設計する必要があります。
特に注目されているのがゾーニングの考え方です。業務に応じたエリアを明確に区切ることで、集中力を必要とする業務には静かなゾーンを、活発な議論を交わす業務には開放的なミーティングスペースを設けるなど、業務特性と空間が一致するような配置が求められています。このようなレイアウトは、単なる空間の分割ではなく、社員の行動特性や心理的ストレスにも配慮した設計です。
オフィスにおける動線も機能性を左右する重要な要素です。日常的に使用するプリンターや書類棚、会議室などへのアクセスがスムーズであるかどうかが、業務効率に大きく影響します。動線の短縮によって移動時間を減らし、無駄を省くことで、社員がより本来の業務に集中できるようになります。
以下は、オフィスレイアウトの機能性を高める要素を整理したものです。
| 要素 | 配慮すべきポイント | 効果 |
| デスク配置 | 通路幅や視線の抜け、背面の圧迫感を軽減 | 長時間作業でも疲れにくく、集中しやすい |
| チームの近接配置 | 部署間の連携・会話頻度に合わせて調整 | コミュニケーションの活性化 |
| リフレッシュスペース | 社員の休憩・気分転換のための明るい空間 | メンタルヘルスの維持、業務集中力の向上 |
| 執務ゾーンの静音化 | 音を遮るパネルや家具の配置 | 集中力の高い作業空間の実現 |
| 通路・動線の整理 | 人の行き来が多い場所のレイアウト最適化 | 接触回避や移動ストレスの軽減 |
こうした設計は、デザイン性だけではなく、日々の業務効率を高める機能性に直結します。ゾーニングにより静と動のエリアを明確にし、それぞれのエリアに適した設備や家具を導入することで、空間そのものが業務を支援する要素となります。
空間設計を進める際には、座席の配置だけでなく、オフィス内の空気の流れや照明の分布、音の反響などにも配慮が求められます。チーム単位での配置と個人の集中スペースを両立させるには、間仕切りを活用したハイブリッド型レイアウトが有効です。これはフリーアドレスとの相性もよく、柔軟な働き方を実現するための仕組みとして多くの企業が導入しています。
社員にとって快適でありながら、企業としての生産性を最大化するオフィス空間。それを形にするためには、ゾーニング・動線・空間効率のバランスを考慮しながら、一つひとつの配置や家具選定を丁寧に行うことが求められます。
少人数オフィスで効率を上げる配置の工夫
1人から10人までの使いやすい座席構成
小規模なオフィスにおいて効率的な座席配置は、生産性や快適性に直結する重要なテーマです。人数が限られているからこそ、空間の無駄をなくし、動線やコミュニケーションの取りやすさを意識した設計が求められます。座席の構成には、業務内容やチーム構成、フリーアドレスの導入有無などが大きく関わってきます。
1人から10人規模のレイアウトでは、まず業務の特性を明確に把握することが鍵となります。たとえば、リモート中心のスタッフと出社頻度が高いスタッフが混在する場合、それぞれに適した座席の確保が必要です。完全固定席にこだわると空間効率が下がりやすいため、予約制のフリーアドレス制を併用することで柔軟に対応できます。
以下に、人数別の座席構成とポイントを整理したものを掲載します。
| 人数規模 | おすすめ配置形式 | 特徴 | 留意点 |
| 1〜2人 | L字型デスク配置 | デスクワークと収納を両立できる | 壁面収納やチェア選定に注意 |
| 3〜5人 | 対向型または島型 | コミュニケーションを重視した構成 | 通路幅と集中エリアの分離が必要 |
| 6〜8人 | パーティション併用型 | 半個室感を出しながら交流を保てる | パネルの高さと設置位置が重要 |
| 9〜10人 | フリーアドレス+固定席混合 | 柔軟な運用が可能なハイブリッド構成 | 執務スペースと休憩スペースの比率を調整 |
対向型や島型の座席配置は、少人数でもチーム感を保ちやすく、日常的な会話や情報共有がスムーズになるというメリットがあります。しかし一方で、集中したい作業時に視線が交錯したり、雑音がストレスになるケースもあります。こうした場面に備え、各デスクの間隔を工夫したり、視線を遮る簡易な仕切りを用いることで解消可能です。
座席のサイズ感やレイアウトの寸法バランスも重要です。デスクの幅や奥行き、チェアの可動範囲を想定し、十分な通路を確保しながら座席を配置することが、快適なオフィス環境をつくる基本となります。
少人数オフィスでは収納スペースが限られるため、デスク下の引き出しや縦型ラック、壁面収納などを積極的に取り入れると、作業エリアを広く保てます。必要に応じてミーティング用テーブルを共用エリアに配置し、来客や短時間の打ち合わせに対応できる体制を整えておくのも有効です。
社員が安心して長時間座れるよう、チェア選びも重要です。腰への負担を軽減する機能性チェアや、肘置き付きで姿勢を安定させるタイプなど、オフィスワークの実態に即した選定が求められます。
少人数ならではの特徴として、空間をチームごとのカラーでゾーン分けしたり、共通の掲示板を設けて全体の一体感を生む工夫も効果的です。こうしたアイデアの積み重ねが、快適性と効率性を両立する配置づくりに繋がっていきます。
家具や設備を活かす配置の工夫
デスクやチェアの寸法と間隔の考え方
オフィスの快適性と効率性は、家具の寸法とその配置によって大きく左右されます。特に限られたスペースの中で複数の社員が日常的に作業を行う場では、適切なデスクの大きさやチェアとの間隔、通路の確保など、細部への配慮が不可欠です。業務の内容や頻度、使用する道具の種類、移動の動作範囲などを踏まえた上で、レイアウトの寸法バランスを慎重に検討することが求められます。
基本的な寸法の目安として、一般的なオフィス用デスクの幅は1000〜1400mm、奥行きは600〜700mm程度が多く採用されています。チェアの奥行きや背面のスペースを考慮すると、後方に最低でも800mm以上の余白が必要です。この空間は、座る・立つという基本動作を妨げないだけでなく、背後を通る人の安全な通行にも繋がります。通路に関しても、主通路は1000mm以上、補助的な通路であっても800mm以上を確保すると移動がスムーズになります。
以下は、レイアウト設計時に考慮すべき主要寸法の参考値をまとめたものです。
| 設置対象 | 推奨寸法(目安) | 説明 |
| デスクの幅 | 1000〜1400mm | 業務内容により可変、モニター2台設置なら広めに |
| デスクの奥行き | 600〜700mm | 書類やキーボード操作に必要 |
| チェア背面の余白 | 800〜1000mm | 通行・動作のための最小限の空間 |
| 通路幅(主) | 1000〜1200mm | 毎日使う通路。すれ違い可能な余裕が必要 |
| 通路幅(副) | 800〜1000mm | 収納・個室横など補助通路 |
寸法の設計は単なるルールにとどまらず、業務効率やストレス軽減にも大きく影響します。たとえば、隣同士のデスクが近すぎると作業中に肘がぶつかったり、物音が気になったりと集中を妨げる要因にもなります。逆に広すぎると無駄なスペースとなり、冷暖房効率の低下や動線の長文化を招く恐れもあるため、バランス感覚が重要です。
固定レイアウトかフリーアドレスを導入しているかによっても考慮すべき点は変わります。固定席の場合は個人の荷物や資料が増えがちなため、個人収納のスペースを確保する必要があります。フリーアドレスではデスク下収納を減らし、共有棚やロッカーとの動線を意識することが求められます。社員の利用頻度や部署ごとの業務特性を把握し、それに合わせた寸法の最適化が、日々の業務を快適に支える基盤となります。
家具メーカーのカタログに掲載されている推奨寸法も参考になりますが、自社オフィスの現状と照らし合わせた「実測」が最も重要です。将来的な人員増加や席替えの可能性を想定し、ある程度の柔軟性をもたせたレイアウト設計も現代オフィスにおいては欠かせません。
職場の雰囲気に合わせた空間の演出
おしゃれさと落ち着きのバランスを考える
オフィスの空間づくりにおいて、見た目の美しさと働く環境としての落ち着きは、どちらか一方に偏ってしまうと社員のモチベーションや業務効率に影響を与えます。おしゃれで洗練された空間を演出する一方で、集中できる空気感も保つ必要があります。このバランスを取るには、色や素材、照明といった視覚的要素と感覚的な快適さを意識した設計が欠かせません。
配色においては、白やグレーをベースに木目調の家具やナチュラルカラーを取り入れることで清潔感と温かみが両立されます。ビビッドな色はアクセントとして小物やチェアなどに使用するのが効果的で、刺激とリラックスの調和を図れます。ガラスパーテーションや観葉植物を活用することで視線の抜けを確保し、空間の閉塞感を軽減できます。これはストレス軽減にもつながり、心理的にも快適なオフィスづくりの一環となります。
素材選びにおいては、床材やデスク表面の質感が印象に直結します。光沢のある人工素材よりもマットな木質素材の方が落ち着いた印象を与える傾向があります。チェアや家具の背面素材も重要で、視界に入る面積が多い部分は全体の印象に大きく作用します。手触りや質感といった触覚的な快適さも含めて、家具の選定には専門的な視点が求められます。
光の取り入れ方も空間の印象を大きく左右します。自然光が入る窓際には執務エリアを配置し、日中は外光を活用することで目の疲れを軽減します。反対に、照明が必要な場所では昼白色の照明と電球色を組み合わせ、時間帯や業務内容に応じて調光可能な環境を整えることで集中とリラックスを切り替えられます。照明の温度と配置は業務効率だけでなく、社員の精神的安定にも関わる重要な要素です。
このような視覚と感覚の要素は、表にまとめると以下のようになります。
| 要素 | 推奨スタイル例 | 目的と効果 |
| 配色 | 白×木目×アクセントカラー | 清潔感と安心感、集中力の維持 |
| 素材 | マット調・木質系 | 視覚的な落ち着き、触感による快適性 |
| 照明 | 自然光+昼白色+電球色 | 業務効率とリラックスの両立 |
| 観葉植物 | 中低木を中心に配置 | ストレスの軽減、空気の浄化 |
| パーテーション | クリアガラスまたは半透明素材 | 圧迫感を軽減しつつ視界を遮る |
こうした演出を導入するにあたっては、見た目だけでなく、実際の業務動線や音環境とのバランスにも配慮する必要があります。共有スペースにカラーラグを敷くことで空間を視覚的に区切ったり、吸音素材の壁材を採用することで声の反響を抑え、落ち着いた雰囲気を保ちます。社員が無意識に感じる快適さの追求が、結果的に生産性と職場満足度の向上につながるのです。
企業のブランドやメッセージ性をインテリアに反映させることで、訪問者に対する印象を形成し、社員に対しても帰属意識を高める効果が期待できます。会社のミッションカラーを使った壁面や、沿革をデザイン化したパネル展示など、オフィス空間を企業文化の発信地として活用するケースも増えています。見た目の印象に加えて、意味づけを伴ったデザインがより深い価値を生むのです。
オフィスにおける「おしゃれさ」と「落ち着き」は相反するものではなく、計画的な設計により共存可能です。心地よさを感じながらも、業務への集中を促す空間設計こそが、これからの時代に求められるオフィスの姿といえるでしょう。
まとめ
快適で効率的なオフィス環境を実現するためには、単にデスクや家具を並べるだけでは不十分です。働く人々の業務内容やチーム構成に応じた柔軟なレイアウト設計こそが、生産性やモチベーション向上の鍵を握ります。
社員が日常的に使用するワークスペースや会議室、コピー機などの設備の位置関係を考慮した動線の最適化は、移動時間や業務の無駄を減らすだけでなく、自然なコミュニケーションの促進にもつながります。フリーアドレスの導入やゾーニングの工夫によって、集中力を要する作業と活発な打ち合わせを同時に成立させる空間づくりも可能です。
通路幅やデスク間の間隔、寸法の基本を守ることは、安全面の確保にも直結します。業務に支障をきたすような狭すぎるスペースや、動線が交差して混雑するエリアが存在するレイアウトは、社員にストレスや疲労を与え、結果的に生産性の低下を招く可能性があります。
自社の働き方に合ったオフィスレイアウトは、部署ごとの業務フローやコミュニケーションのスタイルに応じて、最適化されていくべきものです。業種や職種によって必要なスペースや空間構成も異なるため、テンプレート的なレイアウトではなく、自社特有の要件を踏まえた柔軟な設計が求められます。
今あるスペースの中で、業務効率を高めつつ快適な環境を整えたいと考えているなら、まずはレイアウトの見直しから始めてみてください。目に見えにくい非効率の改善こそが、長期的な成果に結びつきやすいポイントです。
株式会社ビルプランナーは、お客様のニーズに合わせた不動産仲介サービスを提供しております。テナントの物件探しから不動産の売買、有効活用のコンサルティング、そして賃貸ビルやマンションの建物管理まで、幅広いサービスでサポートいたします。市場動向の精密な分析と豊富なデータに基づき、お客様の不動産活用をトータルでサポートします。どうぞお気軽にご相談ください。
-
-
会社名 株式会社ビルプランナー 住所 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番14号 電話 052-218-4555
よくある質問
Q. 小規模オフィスで10人以下の場合、どのようなレイアウトが効率的ですか
A. 人数が10人以下の小規模オフィスでは、フリーアドレス型の配置や対向型デスクの採用が一般的ですが、作業スペースの性質によって最適な配置は異なります。たとえば、チーム単位でのコミュニケーションが多い業務では、島型レイアウトが有効です。集中力を要する業務が中心の場合は、パーテーションや個別ブースの設置による集中エリアの確保が推奨されます。限られた面積の中でもmm単位でデスクの間隔や通路幅を調整することで、快適性と安全性を両立できます。
Q. オフィスの印象を左右するおしゃれなレイアウトにしたい場合、どんな要素を取り入れるべきですか
A. おしゃれなオフィスレイアウトを実現するには、カラーコーディネート、素材の質感、自然光の取り込み方など視覚的な要素をトータルで設計することが重要です。エントランスや打ち合わせスペースにデザイン性の高い家具を配置することで、企業のブランドイメージを強調できます。近年では、グリーンの設置やナチュラル素材の内装も人気で、モチベーション向上や来客時の印象づくりにも寄与します。雰囲気だけでなく、業務効率とのバランスも大切にしながら、空間全体のコンセプトを明確に設計することが成功のポイントです。
Q. レイアウトの変更で業務効率が本当に上がるのか不安です。効果的な改善例はありますか
A. オフィスレイアウトの改善によって得られる業務効率の向上は多くの企業で実感されています。たとえば、コピー機と会議室の距離を最短化するだけでも移動時間が削減され、ミーティングまでの段取りがスムーズになります。集中エリアとリフレッシュスペースを明確に分けることで、社員の集中力維持とオンオフの切り替えがしやすくなります。実際に、動線の再設計や座席の配置変更によって、報告や相談の回数が増えたという事例もあり、コミュニケーションの活性化にも効果があります。設置や配置の見直しは見過ごされがちですが、執務スペースの改善は業務効率を高める有効な手段です。
会社概要
店舗名・・・株式会社ビルプランナー
所在地・・・〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
電話番号・・・052-218-4555
- 最近の記事
-
-
2026年1月15日オフィスチェアクッションのおすすめ人気と選び方!
-
2026年1月12日オフィスチェアが疲れない選び方と長時間作業で快適に過ごすための比較ガイド
-
2026年1月9日オフィス設計の基本や最新事例を徹底解説!費用や具体的手順もわかる
-
2026年1月3日オフィスの内装工事の業者比較ポイントを解説!
-
- アーカイブ
-
- 2026年1月 (5)
- 2025年12月 (10)
- 2025年11月 (10)
- 2025年10月 (10)
- 2025年9月 (10)
- 2025年8月 (10)
- 2025年7月 (10)
- 2025年6月 (10)
- 2025年5月 (10)
- 2025年4月 (10)
- 2025年3月 (10)
- 2025年2月 (10)
- 2025年1月 (9)
- 2024年12月 (8)
- 2024年11月 (10)
- 2024年10月 (10)
- 2024年9月 (10)
- 2024年8月 (10)
- 2024年7月 (8)
- 2024年6月 (9)
- 2024年5月 (6)
- 2024年4月 (10)
- 2022年1月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 202年1月 (1)