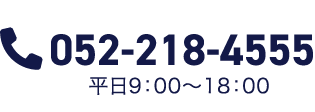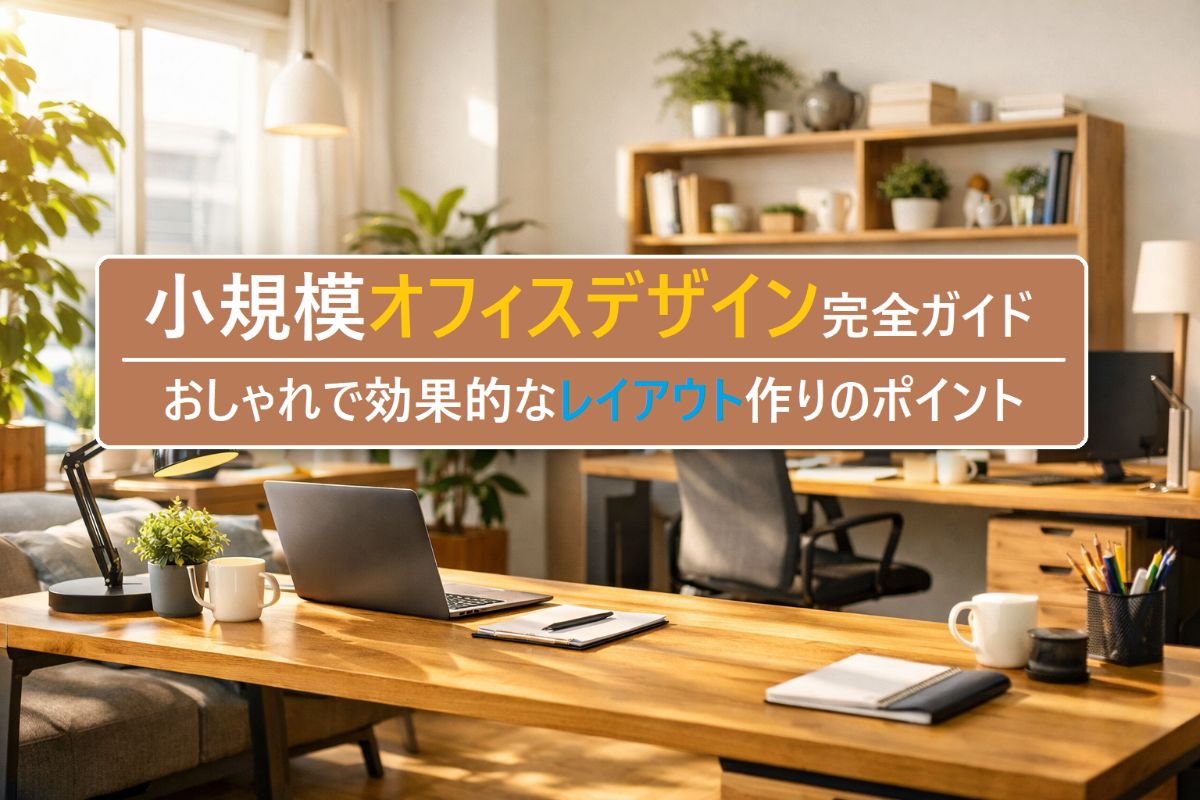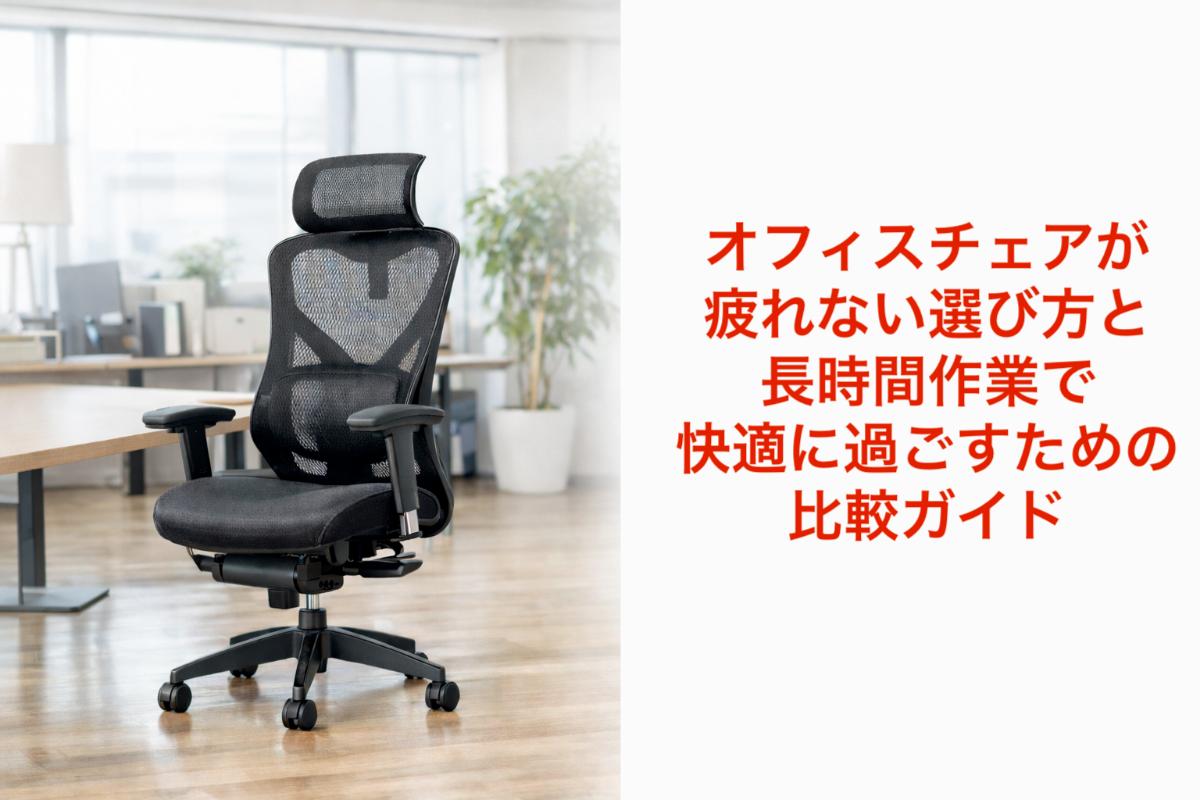不動産コラム
2025年8月9日
オフィスにおけるルクスの基準や照度管理を徹底解説!健康と生産性を高める照明の選び方

オフィスの照明が「なんとなく暗い」「目が疲れる」「作業効率が下がった気がする」と感じたことはありませんか?実は、オフィスの照度(ルクス)が適切でない場合、【従業員の生産性や健康に大きな影響】を及ぼします。
厚生労働省やJIS規格では、事務所作業には300ルクス以上、会議室やリフレッシュスペースにも明確な基準が設けられています。しかし多くの職場では、照度不足や過剰照明が見逃されがちです。
適切な照度の管理は、「快適な職場環境」と「健康な働き方」を両立させ、企業全体のパフォーマンス向上にも直結します。最新の照度測定方法やLED照明の選び方、照明基準の具体的な数値まで、この記事では専門家の視点と公的データをもとに徹底解説。
照明環境を見直すことで、無駄なコストや健康リスクの回避も実現できます。今こそ、照明の基準と管理を根本から見直し、あなたの職場を理想的なオフィス空間へと進化させましょう。
株式会社ビルプランナーは、お客様のニーズに合わせた不動産仲介サービスを提供しております。テナントの物件探しから不動産の売買、有効活用のコンサルティング、そして賃貸ビルやマンションの建物管理まで、幅広いサービスでサポートいたします。市場動向の精密な分析と豊富なデータに基づき、お客様の不動産活用をトータルでサポートします。どうぞお気軽にご相談ください。
-
-
会社名 株式会社ビルプランナー 住所 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番14号 電話 052-218-4555
ルクスの基礎知識とオフィスにおける重要性
照度とは、空間や作業面がどれだけ明るいかを示す指標であり、単位は「ルクス(lux)」です。ルクスは1平方メートルあたりに届く光の量を数値化したもので、オフィスや事務所の快適さや作業効率に直結します。
例えば、300ルクスは一般的な事務作業に必要な明るさとされ、JIS照度基準や労働安全衛生法でも基準値が細かく定められています。正確な照度管理は、職場の安全性と生産性の向上に欠かせません。
ルクスは、光源の種類や設置場所、天井や壁の反射率によっても計測値が変化します。事務所や会議室、リフレッシュスペースなど、それぞれの用途に応じて推奨されるルクス値が異なります。
オフィスで適切な照度を確保することは、作業効率や快適性、健康リスクの低減に直結します。暗すぎる職場は視認性が悪化し、目の疲れや集中力低下を招きます。一方、過度な明るさも眼精疲労やストレスの原因になります。
適切なルクス値の設定は、業務効率を高めるだけでなく、従業員の健康維持にも大きな役割を果たします。
- 目の疲れや肩こりの予防
- 集中力や作業スピードの向上
- 職場の雰囲気や印象の向上
- 健康リスク(視覚疲労、頭痛、睡眠障害など)の軽減
これらのポイントから、オフィスルクスの基準や管理は、単なる照明設計を超え、企業全体の生産性やブランド価値を左右する重要なテーマとなっています。
オフィスで求められるルクスの目安と基準 – 最新法令・規格と推奨値を解説
オフィス照明の適切なルクス基準は、労働安全衛生法やJIS規格によって明確に定められています。労働安全衛生法では、事務作業を行う場所の照度は最低でも300ルクス以上が必要とされており、JIS Z9110では用途や作業内容ごとに細かく推奨照度が設定されています。これにより、オフィス内の照明環境が作業効率や健康に及ぼす影響を抑え、快適な職場環境を維持することが求められています。
労働安全衛生規則第604条では、事務所や工場などの作業スペースで必要な照度基準を明記しています。例えば、一般的な事務作業には300ルクス以上、精密作業には1,000ルクス以上が推奨されています。JIS Z9110の最新改正では、作業面の明るさだけでなく、照度の均一性やグレア(まぶしさ)対策、LED照明の導入など、現代のオフィス環境に合わせた内容が追加されています。これらの基準を満たすことは、法令遵守だけでなく職場の快適性や安全性の確保にも直結します。
オフィス内の各エリアによって、最適なルクスは異なります。執務室では300〜500ルクス、会議室や打合せスペースも同等の明るさが推奨されます。リフレッシュスペースや休憩室は200ルクス程度が目安です。エントランスや通路は100〜200ルクスが一般的です。用途ごとに適切な照明計画を立てることで、目の疲労軽減や職場全体の雰囲気向上につながります。
下記の表は主要なオフィス空間別の推奨ルクス値をまとめています。
| オフィス空間 | 推奨ルクス値 |
|---|---|
| 執務室(事務所) | 300〜500 |
| 会議室・打合せ室 | 300〜500 |
| リフレッシュスペース | 150〜200 |
| エントランス・通路 | 100〜200 |
| 精密作業エリア | 1,000以上 |
300ルクスは一般的なオフィス事務作業で必要とされる最低限の明るさです。500ルクスになると、書類作成や細かな作業がより快適に進みます。1,000ルクスは精密な設計や検査など、細部まで目を使う作業に適しています。明るすぎると逆に目が疲れる場合もあるため、用途と空間に合った照度選びが大切です。
具体的な明るさの比較と適用場面
- 300ルクス:一般的な事務机、パソコン作業
- 500ルクス:会議資料の確認、手書き作業、細かな打合せ
- 1,000ルクス:製図や設計、品質管理、精密検査
このように、部屋の用途や作業内容に合わせて適切な照度を選ぶことで、作業効率と快適性の両立が可能になります。職場ごとに実際の照度を測定し、必要であれば照明器具の追加や配置変更を検討することが推奨されます。
オフィスの照度測定・管理の実践ノウハウ – ルクス測定方法と維持のコツ
オフィス照度の適切な管理には、正確な測定が欠かせません。照度測定には「照度計」が必要で、市販品でも十分な精度が得られます。測定方法は、作業面(デスク上など)に照度計を水平に置き、複数箇所で数値を確認します。測定時は照明の全点灯を基本とし、自然光の影響を受けにくい時間帯を選んでください。測定値はルクス(lx)で表示され、推奨基準を下回る場合は改善が必要です。
照度計選びでは、JIS規格に準拠したモデルを推奨します。デジタル表示やデータ保存機能が付いたものは記録管理に便利です。使い方は、計測面にセンサーをしっかり水平に設置し、測定ボタンを押すだけ。複数の測定点で均等に計測し、平均値を出すことで全体の照度レベルが把握できます。注意点として、蛍光灯やLEDのチラつきが測定値に影響する場合があるため、異常値は再測定を行いましょう。
オフィスの照度は労働安全衛生法によって基準が定められており、事務所作業は一般的に300ルクス以上が必要です。定期的な照度測定は、法令遵守と職場環境維持の観点から必須です。測定頻度は最低でも年1回が推奨されますが、新しいレイアウトや照明交換後には速やかに再測定しましょう。規則違反が判明した場合は指導や是正勧告の対象となります。
測定結果は記録として3年間の保存が推奨されています。管理担当者は結果を帳簿やデジタルデータで明確に残し、必要に応じて提出できるようにしておきましょう。万が一、基準未満や測定漏れが発覚した場合、労働基準監督署からの指導や改善命令が行われることがあります。罰則リスクを抑えるためにも、定期的な測定と確実な記録管理が重要です。
快適な職場環境を維持するには、日常的なチェックリストの活用が有効です。例えば「全照明器具の点灯・消灯確認」「照明器具の汚れや故障の有無」「測定値の定期記録」「作業スペースごとの明るさの均一性」など、複数の観点でチェックを行いましょう。照度が低下していた場合は、電球交換や照明追加を速やかに実施することが求められます。
継続的な照度管理を行うためには、担当者を明確にし、月次・四半期ごとに測定スケジュールを設けるのが効果的です。また、オフィスのレイアウト変更や新規入居時は必ず再測定を行い、基準値を維持できているかを確認しましょう。照明器具の定期清掃やLEDへの切り替えも、全体の照度維持に有効です。管理体制を仕組み化することで、安定した快適なオフィス空間が実現します。
| チェック項目 | 頻度 | ポイント |
|---|---|---|
| 照度測定の実施 | 月1回以上 | 作業面と通路を複数点で計測 |
| 照明器具の清掃・交換 | 半年ごと | 汚れや劣化による照度低下を防止 |
| 記録データの保存 | 随時 | デジタル・紙どちらでも可 |
| レイアウト・照明変更時 | 必ず実施 | 変更直後の明るさを再評価 |
リストやテーブルを活用し、現場でもすぐに使えるチェックリストを整備することで、日常のオフィスにおけるルクス管理がより簡単かつ確実になります。
オフィス照明の種類と選び方
オフィスの快適な作業環境を実現するためには、設置する照明器具の種類とその特徴を正しく理解することが重要です。主なオフィス照明器具には、ベースライト、タスクライト、スポットライトなどがあります。用途や設置場所ごとに使い分けることで、照度や雰囲気、作業効率に大きな違いが生まれます。
- ベースライト:天井に設置し、オフィス全体を均一に照らす基本照明。執務スペース全体の照度を担保し、JIS照度基準をクリアするために不可欠です。
- タスクライト:デスク上の作業面など、必要な場所に追加する補助照明。細かい作業や書類確認時に推奨されます。
- スポットライト:受付や会議室、プレゼンエリアなど、特定の場所を強調し印象を高める照明です。空間デザインのアクセントとしても活用されます。
このような器具の特徴を理解し、作業内容や空間ごとに適切な種類を選ぶことが、快適で効率的な職場環境の基礎です。
ベースライト・タスクライト・スポットライトの違い
| 種類 | 主な用途 | 特徴 | 推奨設置場所 |
|---|---|---|---|
| ベースライト | 全体照明 | 均一な明るさを提供 | 執務室・通路 |
| タスクライト | 作業面補助照明 | 集中的に明るさをプラス | デスク・会議机 |
| スポットライト | 強調・演出照明 | 特定箇所を際立たせ印象付ける | 受付・会議室 |
このように、複数の照明を組み合わせることで、オフィス全体の照度レベルを最適化し、快適な職場環境につなげられます。
LED照明を選ぶ際は、オフィスの作業内容や空間デザインに合わせて、適切な明るさ(ルーメン値)や配光(広がり)をチェックすることが大切です。もちろん、JIS照度基準や厚生労働省の推奨値をクリアすることも必須です。
LED照明には「電球色」「昼白色」「昼光色」といった色温度のバリエーションがあります。色温度は空間の印象や作業効率に直結します。
- 電球色(約2700~3000K):リラックス空間や応接室、休憩スペースに適しています。
- 昼白色(約5000K):自然な白色で、執務スペースや一般的な事務所に最適です。
- 昼光色(約6500K):青白くシャープな光で、集中力を高めて細かい作業が必要な場所に推奨されます。
空間や用途ごとに色温度を選び分けることで、オフィス全体の快適性や生産性を高めることができます。
オフィスの明るさがもたらす効果とリスク
オフィスの照明環境が適切でない場合、従業員の健康や作業効率に大きな影響を及ぼします。明るすぎるオフィスは、まぶしさによる眼精疲労や頭痛を引き起こしやすく、暗すぎる場合は集中力の低下や作業効率の悪化、姿勢の悪化に繋がります。特に日本の労働安全衛生法やJIS基準では、事務所の作業面には300ルクス以上の照度が推奨されていますが、実際には基準を満たさない職場も多く見受けられます。
照度が不足していると、目を細めて作業することが増え、慢性的な眼精疲労や肩こりが発生しやすくなります。また、照明の色温度や明るさが不適切だと、日中の眠気や夜間の睡眠障害を招くことも研究で示されています。過剰な明るさは交感神経を刺激し、心理的なストレスやイライラの原因となるため、適切な照度維持は健康管理の観点からも重要です。
オフィスの照度が適切に保たれていると、従業員の集中力や作業効率が明らかに向上します。JISや厚生労働省の推奨値に従い、執務スペースは300〜500ルクス、会議室や作業内容によってはそれ以上の照度が理想的です。適切な照明は視認性を確保し、ミスの低減や作業スピードの向上に寄与します。特に資料の確認やパソコン作業を行う場合は、明るさのムラが少なく、目にやさしい環境が求められます。
快適なオフィス空間を実現するためには、単に照度基準を満たすだけでなく、空間全体のバランスや作業ごとの照明計画も重要です。自然光を取り入れつつ、LEDや調光・調色機能付きの照明器具を活用することで、一人ひとりに合った明るさや色温度を設定できます。天井や壁、デスク周りの反射率にも配慮し、ムラのない均一な明るさを確保することが推奨されます。照明の配置や光源の種類にもこだわることで、職場全体の印象や快適性が大きく変わります。
最近では、健康経営やウェルビーイングの観点からも照明環境の見直しが進んでいます。従業員の健康を守り、長期的な生産性を高めるためには、適切なルクス管理とともに、目の疲れを軽減する工夫やリラックスできるスペースの照度調整も有効です。照明計画を戦略的に進めることで、企業全体の活力や定着率向上にもプラスの効果が期待できます。
- 適切な照度・色温度調整
- 空間全体のバランス配慮
- LEDや調光機能の活用
- 健康を意識した照明設計
このようなポイントを押さえたオフィス照明の見直しが、快適で効率的な職場づくりに直結します。
オフィスのルクスに関する誤解・よくある質問とその解決策
オフィスの照明基準を検討する際、「300ルクス」「500ルクス」など具体的な数値がよく出てきますが、実際どれくらい明るいのか分かりにくいと感じる方も多いです。300ルクスは一般的な事務作業やパソコン作業に推奨される明るさで、書類の文字がはっきり読みやすく、目の負担が少ないレベルです。500ルクスは図面の確認や細かな手作業が多いスペース、会議室などに適しています。
下記の表で主要な部屋ごとの目安を確認してください。
| 作業空間 | 推奨照度(ルクス) | 体感の目安 |
|---|---|---|
| 一般事務所 | 300~500 | 書類やPC作業が快適 |
| 会議室 | 500 | 顔や資料がはっきり見える |
| リフレッシュ | 200 | リラックスしやすい明るさ |
| 休憩室 | 150~200 | 落ち着いた雰囲気 |
| 精密作業 | 750~1500 | 細部まで見やすい |
オフィスのルクスの基準は、作業内容やスペースごとに「快適さ」と「効率性」を両立できることが重要です。
照度の数値は重要ですが、同じ300ルクスでも天井の高さや壁の色、照明器具の配置によって体感は大きく変わります。白い壁や天井の部屋では明るく感じやすく、ダーク系の内装だと同じルクスでも暗く感じる場合があります。また、作業内容によっても最適な明るさは異なります。
- 書類作成やパソコン作業なら300ルクス以上が目安
- 図面確認や手作業が多い場合は500ルクス以上が推奨
- リラックススペースは200ルクス前後でも十分
数値にとらわれすぎず、使用目的や内装・家具の色など「実際にその場で感じた明るさ」も必ずチェックしましょう。
オフィスの明るさが「まぶしい」「暗い」と感じる場合、まずは実際の照度を照度計で測定しましょう。基準に満たない、または基準を大きく上回る場合は、以下の方法で対策が可能です。
- 照明器具の追加や移設で均一な明るさを確保
- LED照明なら調光・調色機能を活用し、作業内容や時間帯ごとに調整
- 机上のタスクライトや間接照明で局所的に明るさを補う
- カーテンやブラインドで自然光の入り方を調節
強いまぶしさには、電球色や昼白色など色温度の切り替えも効果的です。逆に暗すぎる場合は、反射率の高い天井や壁に変更することでも体感照度が上がります。
照度が足りない場合は、以下のような具体策を検討してください。
- 天井照明の増設や高効率LEDへの交換
- タスクライトの設置(デスクごとに明るさを調整可能)
- 調色機能付き照明を導入し、朝昼晩の時間帯や作業特性に合わせて色温度を調整
- スポットライトや間接照明を使い分け、作業面の明るさを強化
照明計画は「全体の明るさ」と「個別作業の最適化」を組み合わせることで、誰もが快適に働ける環境を実現できます。
オフィス照明の最新動向・今後の展望
サステナブルなオフィス環境の実現において、照度管理は重要な役割を担っています。企業が省エネを推進する中で、照明による電力消費は大きな見直しポイントです。オフィスの照度を最適化することで、快適性を維持しつつエネルギーの無駄を削減できます。特に、JIS照度基準や厚生労働省のガイドラインを参考に、作業内容やスペースごとに必要なルクスを設定することが推奨されています。
照度管理の徹底による省エネ効果は、単にコスト削減に留まりません。CO2排出削減や企業価値の向上にも直結します。今後は、環境配慮と従業員の健康・効率を両立させる照明計画が求められています。
省エネを実現するためには、照明器具の選定や設計プロセスに工夫が必要です。LED照明の導入は消費電力を大幅に抑え、長寿命化も図れるため、現代オフィスには欠かせません。人感センサーやタイマー制御を組み合わせることで、必要な時だけ照明を稼働させることができ、無駄なエネルギー消費を防ぎます。
デスクごとやエリアごとに照度レベルを調整するゾーニング設計も有効です。自然光をうまく取り入れることで、日中の照明使用量をさらに削減できる点も見逃せません。これらの取り組みは、温室効果ガス排出量の抑制にも寄与します。
照明分野では最新技術の進化が著しく、オフィス設計にも大きな影響を与えています。LEDの普及に加え、調光・調色機能を持つ照明器具が増え、従業員の好みに合わせて明るさや色味を調整できるようになりました。
特に、働き方改革の流れを受けて、多様な作業スタイルやフレキシブルな空間設計が求められています。照明も、フリーアドレスデスクや共有スペース、会議室など用途ごとに最適な照度設定が行われています。人間中心設計を取り入れた照明計画は、従業員の集中力や快適性を高め、オフィス全体の生産性向上につながります。
IoT技術の導入により、照明の自動制御や遠隔管理が可能となりました。自動調光システムは、外光や室内の明るさに応じて自動で照度を調整し、省エネと快適さを両立させます。人感センサーは、人がいないエリアの照明を自動でオフにすることで無駄を排除します。
近年、照度基準や関連法令は定期的な見直しが行われています。近年ではJIS Z9110の改定や厚生労働省による労働安全衛生規則の最新動向が注目されています。これらの基準は、事務所や工場、倉庫など用途別に細かく設定されており、適切な対応が必要です。
照度基準や関連法令は、社会や技術の変化に合わせてアップデートされています。企業は定期的に自社の照明環境をチェックし、最新の基準に沿った改善を行うことが重要です。今後は、省エネ・健康・多様性を重視したオフィス照明のあり方が一層求められ、持続可能な経営の観点からも、照明環境の最適化が経営課題となるでしょう。
定期的な照度測定や設備の更新を通じて、常に最適なオフィス照度を維持し、快適かつ持続可能な職場環境の実現を目指しましょう。
株式会社ビルプランナーは、お客様のニーズに合わせた不動産仲介サービスを提供しております。テナントの物件探しから不動産の売買、有効活用のコンサルティング、そして賃貸ビルやマンションの建物管理まで、幅広いサービスでサポートいたします。市場動向の精密な分析と豊富なデータに基づき、お客様の不動産活用をトータルでサポートします。どうぞお気軽にご相談ください。
-
-
会社名 株式会社ビルプランナー 住所 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番14号 電話 052-218-4555
会社概要
店舗名・・・株式会社ビルプランナー
所在地・・・〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
電話番号・・・052-218-4555
- 最近の記事
-
-
2026年1月18日小規模オフィスデザイン完全ガイド!おしゃれ&効率的なレイアウトの作り方
-
2026年1月15日オフィスチェアクッションのおすすめ人気と選び方!
-
2026年1月12日オフィスチェアが疲れない選び方と長時間作業で快適に過ごすための比較ガイド
-
2026年1月9日オフィス設計の基本や最新事例を徹底解説!費用や具体的手順もわかる
- アーカイブ
-
- 2026年1月 (7)
- 2025年12月 (10)
- 2025年11月 (10)
- 2025年10月 (10)
- 2025年9月 (10)
- 2025年8月 (10)
- 2025年7月 (10)
- 2025年6月 (10)
- 2025年5月 (10)
- 2025年4月 (10)
- 2025年3月 (10)
- 2025年2月 (10)
- 2025年1月 (9)
- 2024年12月 (8)
- 2024年11月 (10)
- 2024年10月 (10)
- 2024年9月 (10)
- 2024年8月 (10)
- 2024年7月 (8)
- 2024年6月 (9)
- 2024年5月 (6)
- 2024年4月 (10)
- 2022年1月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 202年1月 (1)